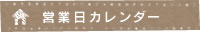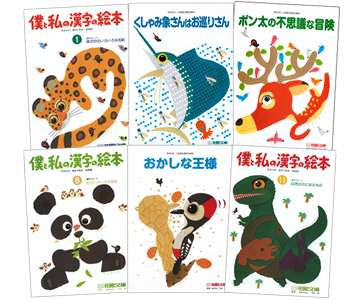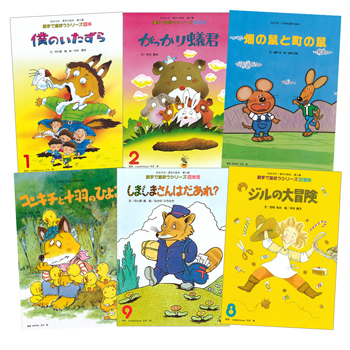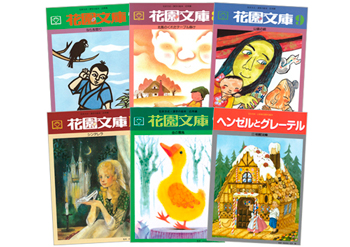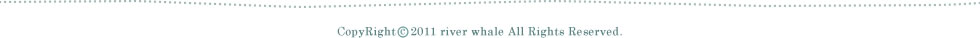大切な我が子へ、今しかできない贈り物を。
言葉の教育は、子供への最大の贈り物です
 Q. どの絵本から始めたらいいの?
Q. どの絵本から始めたらいいの?

リバーホエール絵本館で販売している漢字の絵本は、
大きく分けて
3つの対象年齢に分かれています。
■花園文庫A 僕と私の漢字の絵本シリーズ
<対象年齢:未就園前後>
漢字数:60~100文字前後(同漢字含む)
総文字数:300~350前後
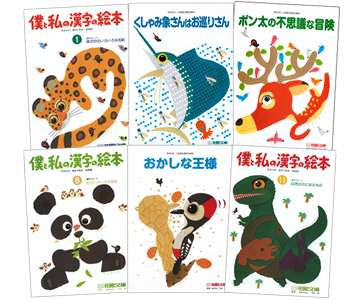
こちらのシリーズは、動物、体の名称など、
各巻に漢字のテーマを設けたシリーズです。
創作童話の中にテーマ漢字が出てきます。
テーマ漢字を使った遊び学習コーナーもあるので、何度も漢字に親しめます♪
漢字学習に重点を置きたい方におススメです。
●お話のタイトル
・
みんな友達(初めて稚園へ行く日のお話)
・
くしゃみ象さんはお巡りさん(くしゃみが止まらない象さんのお話)
・
ポン太の不思議な冒険(紙の汽車に乗り、積木の国へ!)
・
ソフトクリーム食べに(信号など町での注意を学習しよう)
・
おかしな王様(なんも三角にしたい王様のお話)
・
ポポタンのプレゼント(谷で見つけた素敵な贈り物)
■花園文庫B 漢字で遊ぼうシリーズ
<対象年齢:年少前後>
漢字数:80~100前後(同漢字含む)
総文字数:300~450前後
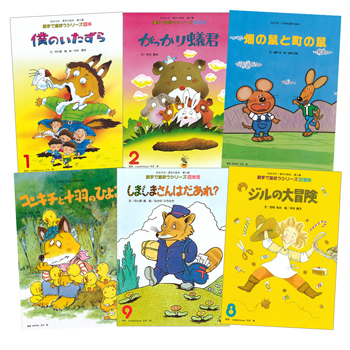
やさしく短い文章の物語で、絵本を読む楽しさ、喜びを味わえるシリーズです。
物語は創作童話が中心で、心を育む内容となっています。
漢字かな交じり文が初めてでも、気軽にお読みいただけます♪
●お話のタイトル
・
僕のいたずら(いたらしたら狼になっちゃった!)
・
がっかり蟻君(大きなった蟻君が起こす大騒動のお話)
・
畑の鼠と町の鼠(田と都会、どっちで暮らしたい?)
・
コンキチと十羽のひよこ(狐がひよこの親に!?)
・
しましまさんはだあれ?(しましまの動物を探すお話)
・
ジルの大冒険(洋服ジルがお菓子島へ)
■花園文庫C・D
<対象年齢:年中・年長前後>
漢字数:200~300文字前後(同漢字含む)
総文字数:1000文字前後
[花園文庫C]
 [花園文庫D]
[花園文庫D]
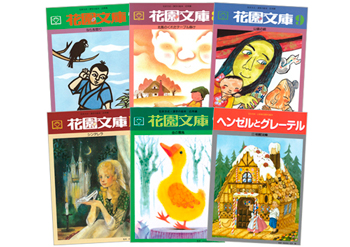
日本と世界の名作童話を漢字かな交じり文でつづる、本格的な童話絵本シリーズです。
文章量のある絵本に興味が出てきたら、ぜひ読んでおきたい名作です♪
●お話のタイトル(花園文庫C)
・
大工と鬼六(鬼の名に悩む大工の目の前に・・・)
・
三匹の子豚(子豚たの行動が教訓を伝えます)
・
天狗の羽うちわ(扇と鼻が伸びるうちわのお話)
・
ジャックと豆の木雲の上の世界は?夢と冒険の物語)
・
聞き耳頭巾(狐にもった頭巾には不思議な力がありました)
・
金の魚(願いを叶え金の魚のお話)
●お話のタイトル(花園文庫D)
・
なら梨取り病の母のために梨を探す兄弟の話)
・
北風のくれたテーブル掛け(楽しい魔法の品がいろいろ出てきます)
・
山婆の錦(皆に恐れれている山婆、でも実は・・・)
・
シンデレラ(夢あふるお話を美しい挿絵と共に)
・
ヘンゼルとグレーテル(お菓子の家が空想の席を広げます)
・
金の鵞鳥(優しい末弟が手に入れた幸運のお話)
<!大切!>
それぞれのシリーズに対して、対象年齢を設けておりますが、決してその順に読んだほうがいいというものではありません。
対象年齢はあくまでも目安として設けています。
成長、環境、興味、関心が、お子様一人一人によって大きく違ってくるのは当たり前のこと。
どうぞ対象年齢にこだわることなく、お子様の興味関心や、普段お子様が読まれている絵本に合わせて、一番楽しめる絵本お選びください。
お子様が興味を示す絵本でしたら、多少文章量の多い絵本でも、親御様と一緒に楽しく読めることと思います。
いろいろな本をたくさん読んであげなければと焦る必要もありません。
お子様が興味を示す一冊に出会ったら、
どうぞ繰り返し、繰り返し、何度でも読んであげてください。
記憶の原理は“関心”と“反復”です。
興味関心が強いほど、反復が多いほど、記憶の定着は強くなります。
漢字を多く教えようとするのではなく、楽しく繰り返し触れる環境をつくってあげましょう。
・・・・・・言葉の教育について(おまけのページ♪)・・・・・・
Q. 漢字はひらがなより難しい?
いいえ、決してそんなことはありません。
そもそも、幼児向けの絵本の多くがひらがなで書かれているのはなぜでしょう。
たとえば、
●にわにはにわにわとりがいる
●庭には二羽鶏がいる
どちらが分かりやすいと感じるでしょうか?
幼児にとって、文字の覚えやすさは、
そのものをイメージできるかどうかであり、字形の複雑さは関係ありません。
幼児にとって
具体的なものほど覚えやすく、抽象的なものほど覚えにくいのです。
漢字は目で見る言葉です。
一字一字が意味・形・音を持っているため
幼児にとって記憶の手がかりを辿ってイメージしやすく、
意味を感じ取りやすい言葉です。
見たもの聞いたものを丸暗記する能力が非常に高い幼児の時期に、
耳だけでなく、目を同時に使って文字を見せることが、
幼児期の言葉の教育でとても大切です。
●記憶について
次のような研究結果が得られています。
ある知らない言葉を・・・
・耳だけを使って覚えた場合、3日後に覚えていた人の割合・・・10%
・目だけを使って覚えた場合、3日後に覚えていた人の割合・・・20%
・目と耳の両方を使って覚えた場合、3日後に覚えていた人・・・65%

幼児期の言葉の教育は、
耳だけに頼るのではなく、目を同時に使って文字を見せることが効果的です。
漢字の絵本は、決して特別な絵本ではありません。
どうぞ、普段読まれている絵本と同じように、お子様に読み聞かせてあげてください。
Q. 読める漢字は書けるべき?
読める漢字は書けなければならない。そんな固定観念はありませんか?
いいえ、そんなことはありません。
書くことは読むことに比べて、たいへん難しいことがわかっています。
幼児期に大切なのは、
特にまず
読むことから始め、言葉をたくさん増やしてあげること。
一緒に絵本を読みながら、
絵の中に大きく表記された漢字を指して教えてあげてください。
文章を指でなぞって読んであげるのも良いでしょう。
まだ文字に関心がなければ、それらは必要ありません。
読みの学習が繰り返され、字形の認識が深まるにつれ、
やがてお子様が一人で、漢字の絵本を読むようになるでしょう。
幼児期は、まず読むことから。書けなくてもいいのです。
おすすめの絵本